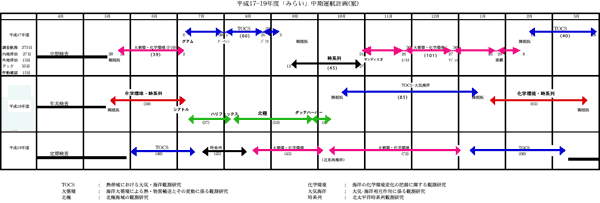| 平成17-19年度「みらい」中期観測研究計画概要 |
平成16年6月4日
| 1. 運用の基本方針 海洋地球研究船「みらい」の運用は、海洋開発審議会第4号答申「我が国の海洋調査研究の推進方策について(平成5年12月)に述べられている4つの重点基盤研究テーマ(熱循環の解明、物質循環の解明、海洋生態系の解明、海洋底ダイナミクスの解明)を推進する事を主な目的としている。実際の運航計画の作成に当っては、「長期観測研究計画(平成10年2月)」の下に3年間の「中期運航計画」が作成され、それを下に毎年の研究公募がなされる。 2. 海洋研究開発機構を取り巻く状況 総合科学技術会議が策定した科学技術基本計画(平成13年3月)には、「科学技術は人類の未来を拓く力」として21世紀の地球変動に対応することが謳われ、その戦略的重点四分野の一つに「環境」が挙げられている。この様な下で、科学技術・学術審議会答申「21世紀初頭における日本の海洋政策」(平成14年8月)には、海洋政策の三本柱を「海洋を知る」「海を守る」「海を利用する」としており、「地球温暖化や気候変動等のメカニズム解明」が「海を知る」(海洋研究)の具体的な推進方策の柱となっている。これに沿って、海洋研究開発機構における海洋観測研究の中期目標及び中期計画は、「水・熱・物質循環過程の観測」と「地球温暖化の影響を検出し、数年から数万年規模での地球環境変動の理解」である。 3. 主要研究課題 「みらい」の次期中期観測研究計画は、日本が進める施策や国際的状況(例えば、CLIVAR+Carbon計画)、更には海洋研究開発機構としての中期目標・計画を踏まえ、熱循環・物質循環過程の観測を中心として太平洋、インド洋、北極海域において、以下の5つの主要研究課題を推進する。
|