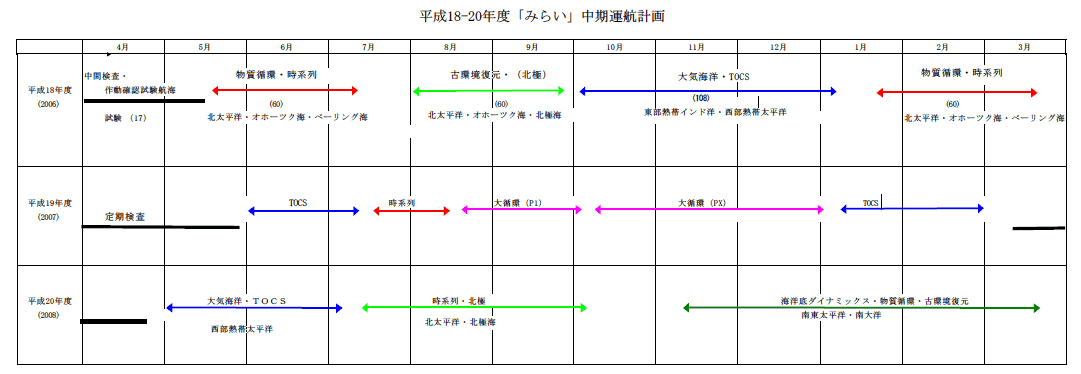| 平成18−20年度「みらい」中期観測研究計画 |
| 1.背景と全体計画 21世紀の人類にとっての大きな課題は、人口・水・食料問題に加えて温暖化に代表される地球規模の環境変動である。科学技術基本計画には、「科学技術は人類の未来を拓く力」として21世紀の地球変動に対応することが謳われ、その戦略的重点四分野の一つに「環境」が挙げられている。この様な下で、科学技術・学術審議会答申「21世紀初頭における日本の海洋政策」(平成14年8月)には、海洋政策の三本柱を「海洋を知る」「海を守る」「海を利用する」としており、「地球温暖化や気候変動等のメカニズム解明」が「海を知る」(海洋研究)の具体的な推進方策の柱となっている。また、総合科学技術会議「地球観測の推進戦略」(平成16年12月27日)では、海洋環境変動の長期観測、海洋二酸化炭素観測網の整備、観測空白域のない地震・津波の定常的・長期的観測網の構築などを戦略的重点課題としている。国際的には、平成15年G8サミット(エビアンサミット)において採択された「持続可能な開発のための科学技術」行動計画に基づいて、平成17年2月の第3回地球観測サミットで「全球地球観測システム10年実施計画」が発表された。この様な背景の下、海洋研究開発機構では海洋に関する基盤的研究開発を通じて、地球温暖化等の地球環境問題の解決、地震・津波等の自然災害による被害の軽減、知識の深化・拡大による社会経済活動の発展・国民生活の質の向上等に貢献すること中期目標に掲げている。 この中期観測研究計画では「みらい」長期観測研究計画を基に、地球環境観測研究として「数年から数万年規模での気候変動に対する海洋の役割」と「気候の自然変動と温暖化に代表される人為起源の変化の相違」を明らかにするための諸課題を、海洋底ダイナミクス研究として、海域の地震・火山活動を引き起こす地球内部の動的挙動(ダイナミクス)についての現象と過程に関する課題を取り上げた。このため、向う3年で下記の7件の主要研究課題により太平洋、インド洋、北極海域等においての観測研究を行う。 2.主要研究課題 (1)太平洋・インド洋熱帯域の観測研究 西部熱帯太平洋域及び熱帯インド洋域は、エルニーニョ現象、アジアモンスーンやダイポールモード現象に代表される気候変動を引き起こす大気・海洋現象が起こる場所であり、地球規模の気候変動現象を解明する鍵を握っている。そこで、H18年度からH20年度の「みらい」の航海ではトライトンブイの維持を行い、エルニーニョの源である西太平洋からインド洋にかけての暖水プール域において、海洋および大気の熱と淡水の空間分布と時間変化を把握し、その変動機構について研究を進める。またH18年度の航海では後述主要課題「大気−海洋相互作用に係る観測研究」と連携し、インド洋において降水システムの観測を主眼とした大気と海洋表層の集中的な観測を実施する。 (2) 大気−海洋相互作用に係る観測研究 熱帯海洋上では、主に大気−海洋相互作用を介して積雲対流が発生・発達し、全球大気大循環の駆動源となっている。そこでドップラーレーダー等を用いて雲・降水システムの発生・発達機構を明らかにすることを目的に観測を実施する。特に暖水プール域では主要な季節内変動であるマダン・ジュリアン振動(MJO)に伴い空間スケール数1,000km、時間スケール数10日にも達する組織化された雲群が卓越する特徴を有し、熱帯だけでなく全球的な影響を持つと言われている。そこでH18年度はMJOに伴う積雲対流のオンセットが見られるインド洋において定点観測を実施し、大気及び海洋の同時集中観測を行う。H20年度にも熱帯海域で観測を実施する。 (3)海洋大循環の長期的変動に関する観測研究 太平洋を主たる研究の場として、大洋スケールでの貯熱量・溶存物質量とその長期的(10年スケール)変動とを定量的に明らかにするため、大洋を縦・横断する大規模な高精度観測(WHP再観測)を、これまで2年おきに実施してきた。この観測は、CLIVAR/Carbon及びIOCCPの枠組みの主要部分を占めており、国際的な調整・協力を背景に実施されている。平成19年度には、WHP-Pl(47゜N)測線に他の1測線(内外の機関と調整中)を組み合わせた観測を計画している 。 (4)北極海気候システムに関わる海洋循環研究 夏季でも海氷の存在を可能としている北極海特有の海洋成層構造の形成過程及びその変動メカニズムの理解を目指す。成層構造を形成する水塊は、夏季及び冬季太平洋水、大西洋水、河川水、融氷水であり、これらの「水塊循環」の理解を中心とした観測を実施する。H20年(2008年)は国際極年(2007〜2008年)にあたり、各国と連携して海氷の減少が顕著であるアラスカ沖の海域を中心に、異種水塊が複雑に交差する太平洋側北極海において、陸棚域から海盆域にかけて観測を行う。 (5)化学物質循環研究 気候変動に密接に関係する海洋中の化学物質循環を把握することを目的として、大気海洋間の二酸化炭素交換過程、表層における炭素固定と鉛直物質輸送過程を定量的に明らかにし、海洋中の物質分布の時間変動・変化を捉える観測を西部北太平洋において実施している。H18-20年度においては、北太平洋時系列観測点での係留観測、北西北太平洋海域の基礎生産力測定等生物要素を含む海洋観測を計画している。 BEAGLE2003の結果、ケルゲレン海台底層水の低塩分化など南極オーバーターンに変化が認められ、地球規模での物質循環に変化が起こりつつあると見られる。その影響は、北太平洋の深・底層水へ確実に現れる。そこでBEAGLE2003の成果を基に、南大洋の物質分布の変動を評価するための高精度多項目観測を、IPY(国際極年観測:2007-2008)の一環として平成20年度に実施する。 (6)古海洋環境復元研究 日本を含めた東アジアの気候変動に密接に関与していると考えられるオホーツク海などの縁辺海を含めた北太平洋高緯度域および北極域において、海底堆積物を採取し、氷期?間氷期スケールおよび地球軌道要素では説明のできない急激な気候、環境変動の実態の復元を目的とする。H18年度はオホーツク海、日本海北部、ベーリング海、北極海を集中的に観測し、H20年度にはH18年度の解析結果との半球比較のために南太平洋高緯度域を計画している。 (7)太平洋南東部海域の海洋底ダイナミクス研究 太平洋南東部には、タヒチホットスポット帯、チリ沖海嶺三重会合点など海洋底ダイナミクス解明の鍵を握る重要な海域が存在する。とくに、チリ沖に存在する海嶺三重会合点周辺海域は海嶺が海溝に沈み込む現場を観測できる唯一の地域である。この海域は南緯45度前後にあたり荒天が予想される海域であり、唯一「みらい」による調査が適していると思われる。この地域の海洋底地球科学的な調査を通じて、海嶺が海溝に沈み込むことによって起る大陸地殻の成長過程を検討する事が可能となる。そのために三重会合点周辺海域においてマルチナロービーム測深装置 を用いた海底地形調査と航走地球物理観測(プロトン磁力計、重力計など)を中心とした総合的な海底地球科学観測をH20年度に実施を計画している。また、船上で作成された海底地形図に基づき、可能な限りドレッジによる岩石試料採取およびピストンコア・マルチプルコアを用いた採泥を試みる。またタヒチホットスポット帯海域における海洋底地球科学観測もあわせて実施する。航海はH20年度に計画する。 |