| 1.航海番号 |
| |

2.主要課題名 |
| 南太平洋および沈み込み帯における地質学・地球物理学的研究ならびにチリ沖における古海洋環境変動復元研究 |
|

3.観測研究の目的 |
| 海洋プレート形成現場である東太平洋中央海嶺(主にチリ沖三重会合点)およびその周辺の南太平洋海域において、地質学的・地球物理学的観測を行い、1)海洋地殻構造と海洋底ダイナミクス(マントル上昇流から海洋地殻形成およびプレート進化過程)の解明、2)若い海嶺の大陸下への沈み込みプロセスの観察によって、大陸地殻形成・進化メカニズム(海嶺衝突帯付近のマグマティズムと沈み込み堆積物フラックス)の解明を行う。さらに、ポリネシア周辺海域において広帯域海底地震および海底電磁気観測を行い、3)ホットスポットの成因やスーパープルームと呼ばれるマントル上昇流の存在を探る。上記海域からさらに高緯度域(フィヨルド内およびマゼラン海峡内を含む)にかけて海底堆積物を採取し、4)北半球で確認されている数十年から数百年スケールで変動するダンスガードオシュガーサイクルと呼ばれる急激な気候変動が南半球ではどのように生じていたのかチリ周辺海域において調査するとともに、5)古環境復元の代替指標の高精度化ならびに現代の水柱における物質循環解明のための調査を行う。また、6)南半球における過去200万年にわたる地球磁場強度の変動の復元も行う。
|
|

4.観測の概要 |
| チリ沖三重点周辺海域から55°Sにかけての南太平洋および、フィヨルド内、マゼラン海峡内において、詳細海底地形調査および航走地球物理観測を行い、高精度の海底地形情報および地球物理学的データを獲得する。船上で作成した地形図に基づき、ドレッジ、ピストンコアを実施し、岩石および堆積物試料を採取する。さらに東太平洋中央海嶺から広がる海洋プレート上において、広帯域海底地震計(BBOBS)および海底電位磁力計(OBEM)を設置し、地球内部からのマントル上昇流等地球内部の変動を観測する。また、チリ沖における生物地球化学的試料採取のため、CTD/採水観測、プランクトン採取、懸濁粒子等の採取を行う。 |
|

5.調査海域 |
|
航海全体では、南緯15度から55度、西経70度から150度付近までの範囲を予定。その中で三重点調査海域は、南緯44度から53度、西経70度から82度、BBOBSおよびOBEM調査海域は、南緯16度から23度、西経140度から148度、古海洋調査海域は、南緯45度から56度、西経66度から76度、古地磁気調査は、南緯40度から60度、西経70度から95度の範囲を中心にそれぞれ行う。
|
|

6.日 程 |
2008年11月25日〜2009年3月16日(108日間)
レグ1:2008年11月下旬〜2009年1月上旬
レグ2:2009年1月上旬〜3月中旬
|
|

7.寄港地 |
| |

8.主要課題提案者 |
レグ1(地球物理観測、古地磁気、海底地震計設置):阿部なつ江(地球内部変動研究センター)
レグ2(古海洋観測):原田尚美(地球環境観測研究センター)
|
|

9.本航海計画の問い合わせ |
レグ1(地球物理観測、古地磁気、海底地震計設置):阿部なつ江(地球内部変動研究センター)
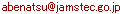
レグ2(古海洋観測):原田尚美(地球環境観測研究センター)
 |
|
|

10.備考 |
|
| レグ1で、チリ沖三重点での地球物理観測、レグ2で、古海洋観測、古地磁気観測、海底地震計設置観測をそれぞれ行う予定である。 |
|
|
|
|